ところで、11月9日のブログには、多摩川白衣観音菩薩の境内で見た古い絵図のことを書きました。
それで今回は、この絵図のなかに描かれてあった「土手」について、あれこれと探ってみようというコンタンです。
結論から話せば
川崎市にあった宮内村を囲っている土手は、この絵図と同じだろう
というのが今回の話です。
そういうことで今回のお題は、
宮内村の土手は絵図にあった
にしました。
今回も文章はできるだけ省略します。
紙芝居を見ているイメージでどうぞ。
では、始まり、はじまりー
まずは、絵図をじっくりと見ましょう。
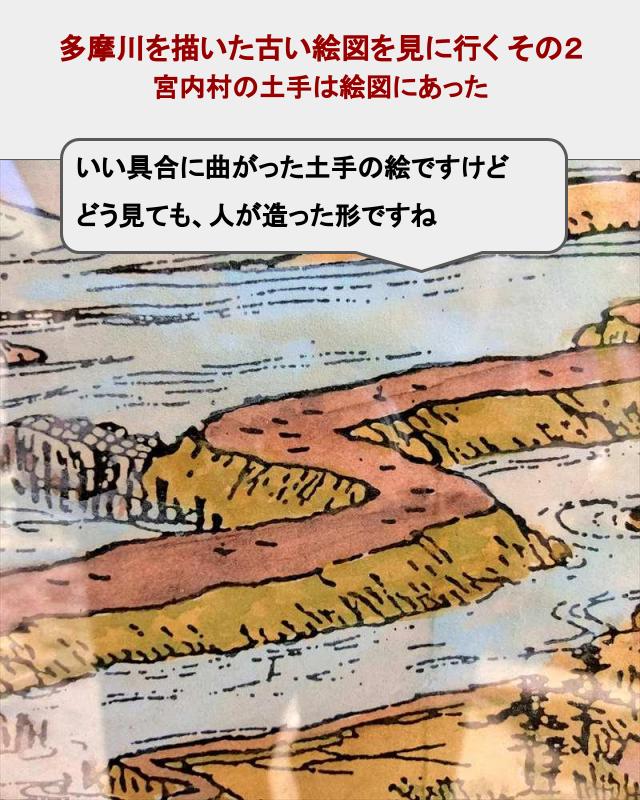
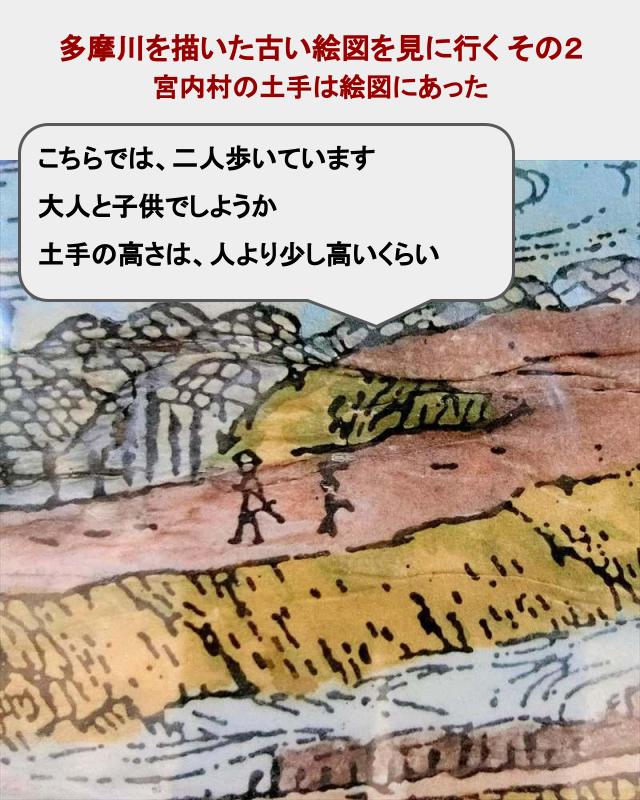
土手の絵をじっくり見たところで、昔のこういう土木工事は、すべて人の手で行ったのですよね。
江戸時代も、明治時代も作業のやり方は、ほとんど同じだったはず。
そうすると、河原の土手の作り方もずっと変わらなくて、おなじ形になったと思います。
そしてつぎの地図が、川崎市にあった宮内村とその土手です。
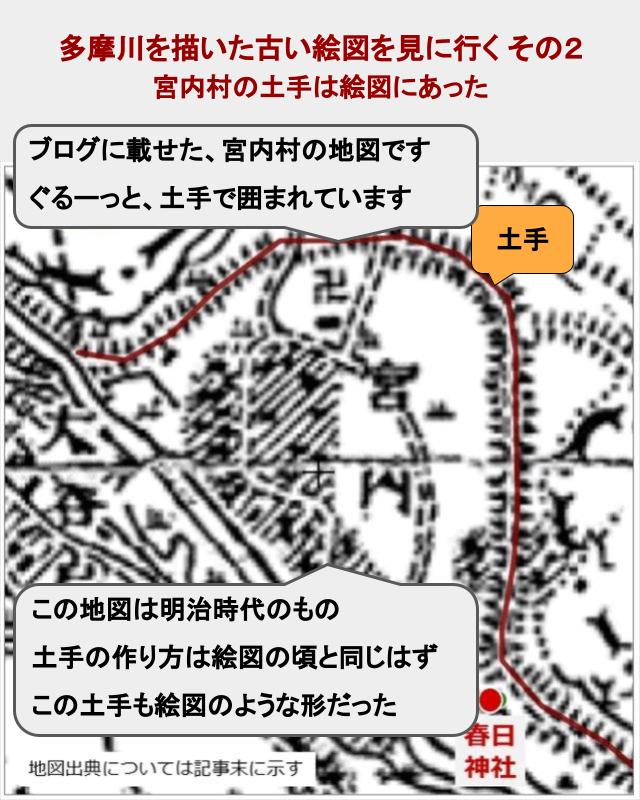
「今昔マップ on the web」 地図
時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」(C)谷謙二により作成されたものから一部を抜粋し、記号等を追記して使用
https://ktgis.net/kjmapw/index.html
さて、ここからは現在の話です。
時代が変わっても人の発想は同じで、ちがうのは、今では機械が作業をするようになったことですね。
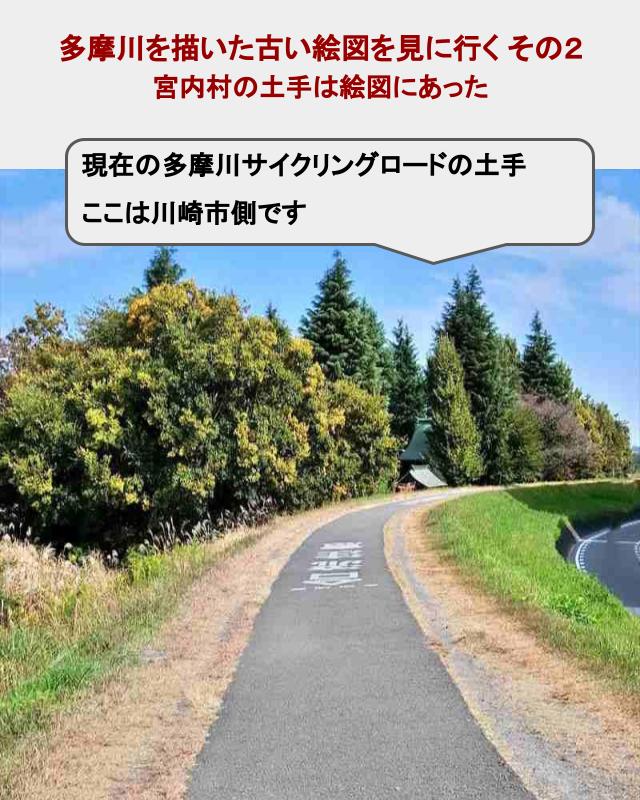
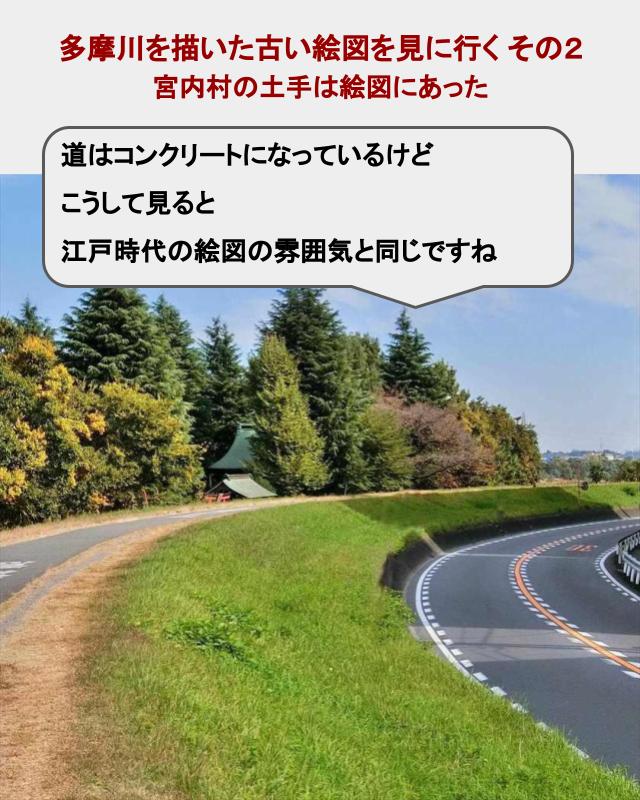
絵図に、土手の上を歩いていた人がいましたね。
その土手の高さは、人より少し高いくらいでした。
そこで、この写真の場所の高さを測ってみました。
なんと、人の背丈と、ほとんど同じでした。
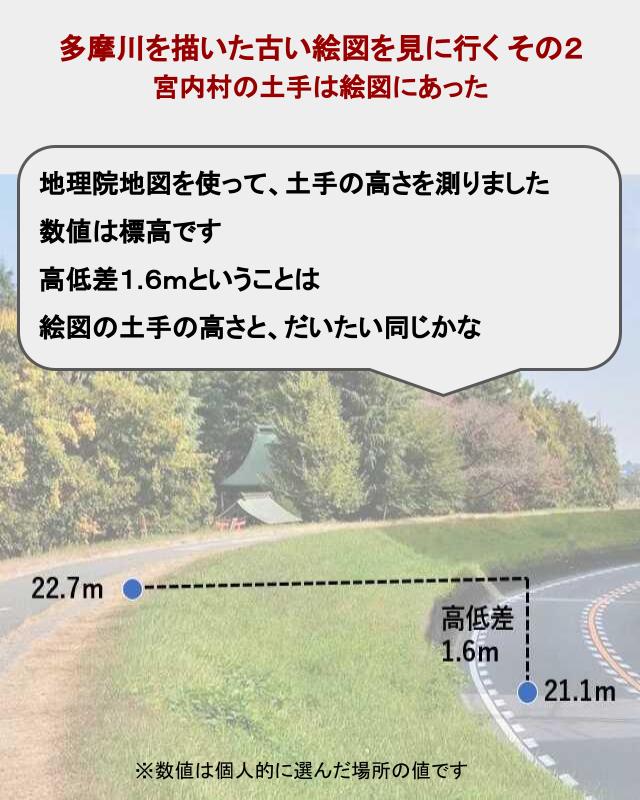
前回のブログ
宮内町のいろいろ
多摩川の筏道をさがして歩きます